「悩み」にどう向き合うか。
それは数多くの書籍で語られてきました。
たとえば「悩みは心の在り方次第」と説く本もあれば、フローチャート式に問題解決を導く本もあります。
今回はその中でも、「向き合うべき悩み」に対して、具体的な解決手法を提示してくれる一冊、
深沢真太郎さんの著書『因数分解思考』をご紹介したいと思います。
書籍『因数分解思考』は以下の方におすすめできる1冊です。
- 向き合うべき悩みがある人
- 向き合うべき悩みのどこから手をつけていいか分からない人
因数分解思考を用いれば悩みの要素を数字に置き換えることが出来ます。
数字にすることが出来たら、取り組みやすく、またコントロール出来る気がするのです。
本記事では『因数分解思考』の概観やメリット・デメリットを紹介します。細かい方法は書籍を参照してください。
因数分解思考とは「悩みを数式にする」ということ
「因数分解」とは、もともとは数式を構成要素(因数)に分ける手法です。
たとえば、数式で言えばxy+xz+y2+yz=x(y+z)+y(y+z)=(x+y)(y+z)
のように、複雑な式を分解してシンプルに捉え直すためのものです。
この発想を「悩み」にも応用しようというのが、本書で紹介されている「因数分解思考」です。
・悩みとはひき算である
深沢真太郎 著 『因数分解思考』 第1章 ”悩みを解決できない”という悩みを解決する対話
(悩み)=(理想)-(現実)
理想と現実に乖離があるほど悩みが大きくなるんですね、分かり易いです。
因数分解思考のメリットを見てみましょう。
因数分解思考のメリット
深沢真太郎 著 『因数分解思考』 第2章 因数分解思考とは何か
目の前に問題(悩み)があった時、そのままではすぐに応えが分からない時もある。
そんな時には、悩みを因数分解して悩みのメカニズムを明らかにすることで、簡単に解決法がだせることもある。
悩みを数式化するメリット
深沢真太郎 著 『因数分解思考』 第4章 あなたの悩みは数値化できる
- 解決の定義ができる
- 解決策がハッキリする
- 間違った努力をしないで済む
因数分解思考の最大のメリットは悩みを視覚化することだと思います。
視覚化することで、解決の道筋がはっきりするのです。
悩みを解決することの5つのステップ
書籍『因数分解思考』で紹介されている悩みを解決するステップが以下です。
「悩みを解決すること」の5ステップ
深沢真太郎 著 『因数分解思考』 第1章 まとめ
1 悩みを定義する(できるだけ具体的に!)
2 悩みのメカニズムを明らかにする
3 悩みを解決するために「仮の正解」を決める
4 仮の正解にたどり着くために、具体的にすることを決める
5 やる
書籍の例題で説明します。
友達が少ないという悩みがあるとします。
【ステップ1】悩みを定義する
悩み=理想-現実
=20人と仲良し-5人と仲良し
=15人と仲よくなれていない
【ステップ2】悩みのメカニズムを明らかにする
仲良し5人=自分と似たタイプ
仲良くなれなかった15人=自分と異なるタイプ
【ステップ3】悩みを解決するために「仮の正解」を決める
自分と異なるタイプの男子とも仲良くする必要がある
【ステップ4】仮の正解にたどり着くために、具体的にすることを決める
親近感(自分から優しく話しかける)
【ステップ5】やる
やる
以上が悩みを解決するステップです。
因数分解思考の注意すべき2点
因数分解思考は有用な考え方ではありますが、注意すべき点もあります。
- 知識がないと悩みのメカニズム解明を間違えたり出来なかったりする
- 数遊びにならないように注意する(因数分解はあくまで手段)
たとえば、「給料の上げ方」を知らないと、「与えられた業務をただこなすだけ」になってしまうかもしれません。
利益構造や評価制度、人間関係について知っていれば、違う戦略も見えてくるはずです。
知識を得るということは、見えていなかったものを見えるようにして「自分の都合のいい解釈」から脱するための手段でもあります。
知識がないと悩みの因数分解を間違えたり出来なかったりする
書籍では「悩みを解決すること」の2ステップ目『悩みのメカニズムを明らかにする』について、以下の様に言及しています。
悩みを解決するという行為は、2つ目のステップが最大の難関になるのだ。
深沢真太郎 著 『因数分解思考』 第1章 ”悩みを解決できない”という悩みを解決する対話
悩みを解決するためには2つ目のステップをより正確にできるかどうかにかかっているわけです。
知識がないと、そもそも悩みのメカニズムを解明出来ませんし間違ってしまうわけです。
再び悩み解決の例題をみます。
【ステップ2】
仲良し5人=自分と似たタイプ
仲良くなれなかった15人=自分と異なるタイプ
もしこの解釈が間違っていたらどうなるでしょうか。
ステップ3の『自分と異なるタイプの男子とも仲良くする必要がある』が見当違いの行動になり、友達は増えないでしょう。
数遊びにならないように注意する(因数分解はあくまで手段)
『2、数遊びにならないように注意する』については以下の通りです。
・数値は道具に過ぎない
深沢真太郎 著 『因数分解思考』 第4章 あなたの悩みは数値化できる
因数分解は目的やゴールではなく、あくまで手段。悩みを具体的に考える必要があるから、具体的な表現ができる数値を使っているに過ぎない。
数値化を目的にしたり、ただの”数遊び”で終わらないように気をつける。
たしかに悩みを数式に変換するだけでは悩みは解決しません。
数値化に変換するのに執着するのはいけなくて、仮の正解をだしたらさっさと試してみることが大事なのです。
悩みを因数分解しているだけでは、人生は良くなっていかないでしょう。自分にとって大事な悩みだけ因数分解すればいいのです。
これが冒頭で『因数分解思考』は『向き合うべき悩みがある方』におすすめといった理由です
自分にとって大事なことについては勉強できるし、モチベーションが湧いてきます。
悩みに対する知識がない時は、AIか専門家に聞こう
知識が足りない点に関しては現代は恵まれています。AIが補完してくれるからです。
今回『やる気』の因数分解を試みました。
本書でも取り扱ってくれています。
(やる気)=(ご褒美の楽しみ)-(やる時の面倒くささ)
深沢真太郎 著 『因数分解思考』 第3章 あなたの悩みは数式で表現できる
(やる気)=(ご褒美の楽しみ)÷(やる時の面倒くささ)
ものすごく共感できる数式です。
この式はご褒美が無いのに、面倒くささが大きいとやる気は萎えてしまうことを表現しています。
しかし、まだ『やる気』の一側面しかとらえられていないと思いました。
chatGPTに聞いてみたら以下の通りになりました。
やる気 = 意義 × 自信 × 魅力 × 環境 × 習慣性
書籍『因数分解思考』の『やる気』の式が『魅力』に組み込まれる感じになるでしょう。
chatGPTの『やる気』は多角的に捉えられています。それぞれの項目を細分化したら、やる気をコントロールできる気がしてきます。
chatGPTの提示してくれた式を見ると、やる気で困っている人が後を絶たないのは、やる気の因数がたくさんあることに原因がありそうです。
やる気について勉強している身として、5つの要素は科学的妥当性の観点からも的を得ていると思います。
私なりにやる気を因数分解してみましたが、途方もない作業になりそうなのでひとまず別記事に譲るとします。
悩みに対する知識がない場合は専門家にたずねるのもいいでしょう。
今ならSNSで簡単に専門家と繋がることが出来ます。
ゼロベースで質問すると門前払いを食らう可能性もありますが、それでも可能性はゼロではないですよね。
専門家といっても自分より詳しい人ならいいと思います。
まずは職場の先輩、上司にたずねてみましょう。
勉強するなら科学的に妥当な知識をつけよう
勉強する方向性で言ったら、科学的に妥当な知識をつけたいものです。
科学的に妥当とされていることは大勢の人に偶然を越えた効果があるからです。
解決したい悩みがあるなら、関連する言葉を検索することをお勧めします。
きっとあなたの悩みを解決するヒントを与えてくれる書籍や研究に出会えます。
まとめ
本記事では、深沢真太郎さんの著書『因数分解思考』をもとに、「悩みを数式のように分解して解決する」というユニークなアプローチをご紹介しました。
● 因数分解思考とは?
- 複雑な悩みを「数式」に見立てて構造化し、問題をシンプルに捉え直す思考法です。
- 例:やる気 = ご褒美 ÷ 面倒くささ
● メリット
- 解決の定義が明確になる
- 解決策がハッキリする
- 無駄な努力を避けられる
● 解決までの5ステップ
- 悩みを具体的に定義する
- メカニズムを明らかにする(ここが最難関)
- 仮の正解を設定する
- 必要な行動を具体化する
- 実行する
● 注意点
- 知識不足だとメカニズム解明を誤る
- 専門家やAIに助けを求めるのも有効です。
- 数値化が目的にならないよう注意
- 因数分解はあくまで手段。悩みを解決するための道具に過ぎません。
書籍『因数分解思考』紹介
「この悩みとは向き合いたい!」そんな時におすすめな一冊です。書籍内では悩みの因数分解の仕方も丁寧に解説してくれているので、興味が湧いた方は是非手に取ってみてください。
おすすめ記事
悩んで眠れない夜はノートに向き合おう↓
手書き一択!自分の大事な事は手間暇かけるべし!手書きで脳を自動検索モードにせよ
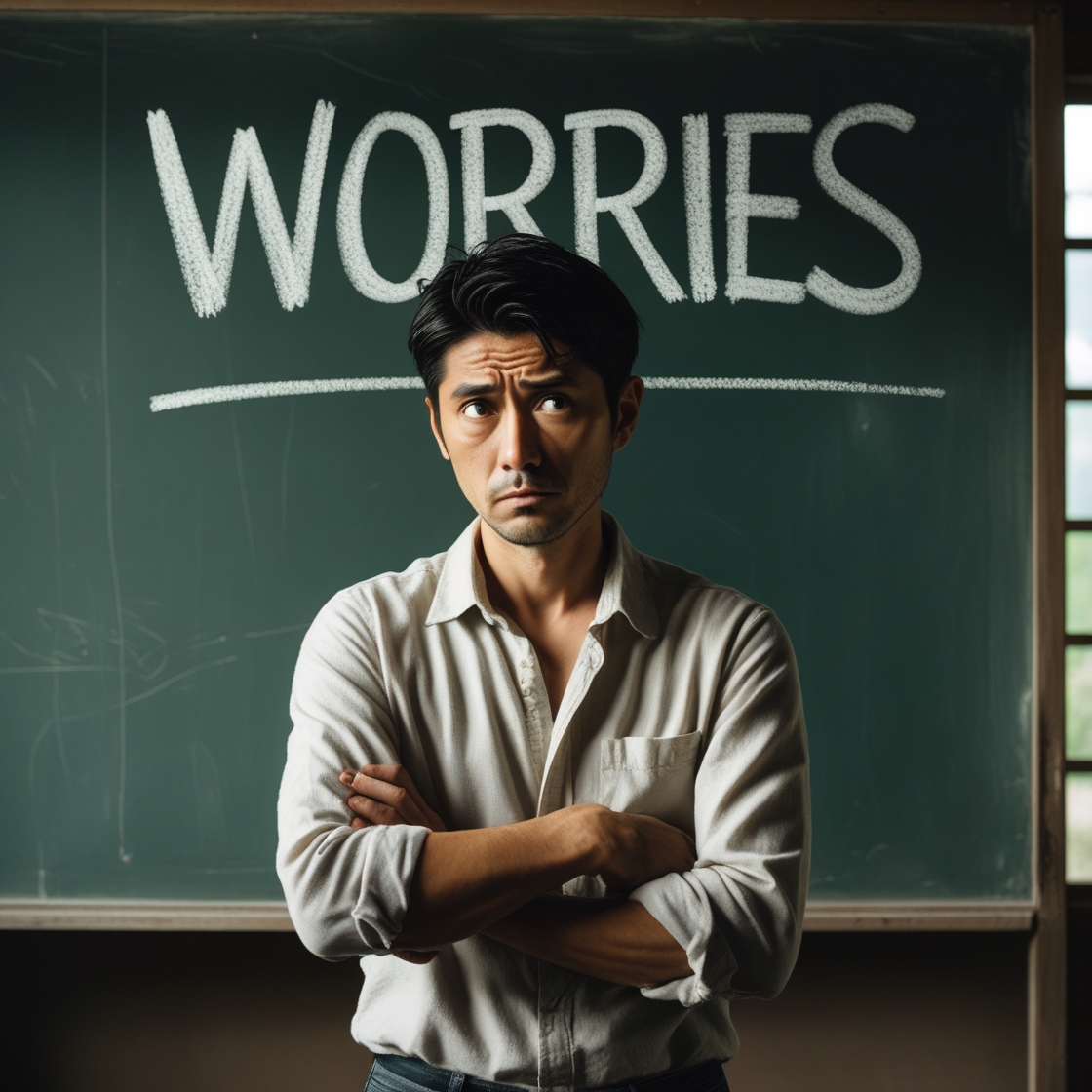


コメント