私は、KOH+の『ヒトツボシ』をきっかけに、東野圭吾の『沈黙のパレード』を手に取りました。『ヒトツボシ』と『沈黙のパレード』はリンクすると知り、歌に触れたときに胸に広がった世界観を、物語の登場人物たちの視点や思考のなかで確かめてみたくなったのです。
現在、読み進めているのは29小節目あたり。そこでは、さおりを大切に思っていた人々が、まるで息を合わせるようにアリバイを作り上げている場面に出会いました。その光景に、私は小さな違和感を覚えました。きっかけは、ほかでもない『ヒトツボシ』でした。
推理パートを読みながら曲を耳にしたとき、ふと気づいてしまったのです。登場人物達はアリバイを示し合わせまっとうな社会生活を送ろうとしている。では、佐織への思いはどこにいってしまったのか。佐織が喜ぶとでも思ったのだろうか。その矛盾の様なもの、私の違和感の正体だったのだと思います。
『ヒトツボシ』からは、復讐の匂いは感じられません。むしろ、そこには切なさと願いがこめられているように響きます。私はこれまで、復讐したいと願ったことがありません。だからこそ、作中の人物の心境がうまく想像できない。もし自分がその立場に置かれたなら、人生を投げ出す覚悟のようなものが必要だろうと思いますが、実際には多くの人を巻き込む形で行動することはできないだろう、とも思います。
それでも小説の中で、登場人物たちは実行に踏み切る。そこに、果たして佐織への思いは残っているのか――。物語はいま、事件の背景が過去へと深くさかのぼり、佐織の事件だけでは収まりきらない広がりを見せています。大切な人を奪われた恨みは、果たして晴らすことが出来るのか。それとも、その後もなお人を縛り続けるのか。彼らは今、どんな思いで過ごしているのか。これからの人物描写に触れるのが、楽しみで仕方ありません。
登場人物は架空の存在ですが、作者は彼らの視点を重ねながら書き進めているのだろうと思います。その一方で、私はふと「生の人間の視点」も欲しくなりました。病気や事件を経験した当事者たちが、自らの言葉で綴った手記――そうしたものを読むのもまた、きっと面白いだろうと思う今日この頃です。
あとがき
私は人の話を聴く仕事をしています。そのなかで、さまざまな人の視点を取り入れることが、きっと自分の糧になるのではないかと思うようになりました。そんな折に出会ったのが、『ヒトツボシ』の世界観でした。そしてそこから自然と、『沈黙のパレード』を読む流れへとつながっていったのです。
小説の登場人物たちは、それぞれに思いや事情を抱えています。その一つひとつに私は「そう思っているんだね」と寄り添う気持ちで読み進めています。肯定も否定もせず、ただ受けとめる。その姿勢は、まるで「聴く」練習をしているかのようです。
やがて私は、架空の物語を越えて、生身の人間の声にもますます耳を傾けたくなっていきました。病気や事件などを体験した当事者が、自分の言葉で綴る手記。その視点に触れることで、自分の「聴く」世界が少しずつ深まっていく――そんな手ごたえを感じています。
この感覚が実に心地よいのです。それは自分が成長している確かな実感なのかもしれません。
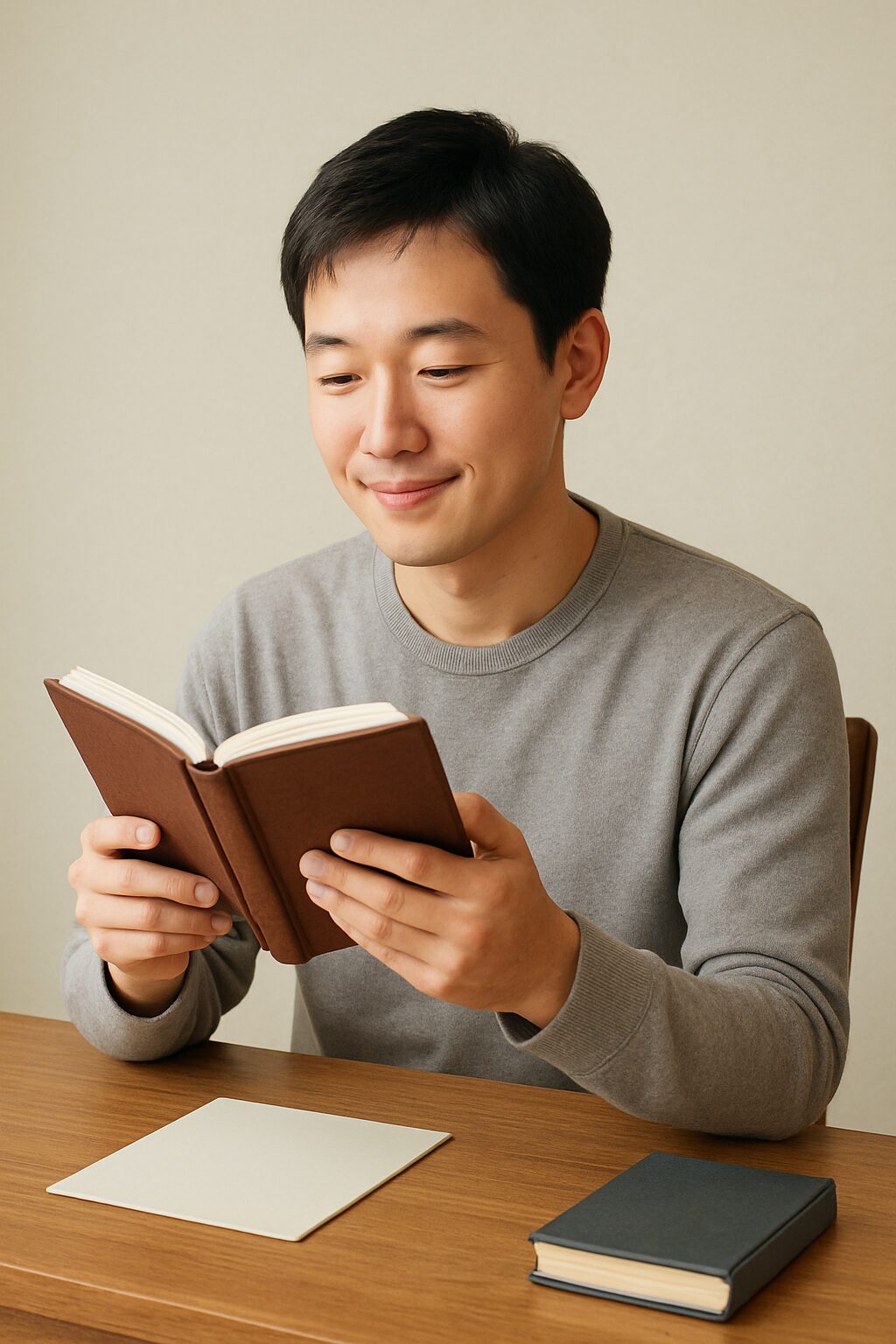

コメント