セッションの中で、「判断すること」と「判断を保留すること」を行ったり来たりしていた日のこと。
不思議とそのときの私の満足度はとても高く、終わった後の充実感が今でも印象に残っています。
さらに話し手の方からも、「「自分の言いたいことが伝わった」と感じた」「またこの人に話したい」と自然に思えた」といった嬉しいフィードバックをいただきました。
これまで「判断せずに聴く」ことを大切にしてきましたが、実際には判断を完全に手放すことはできません。
むしろ、その“行ったり来たり”の中に、聴くセッションの本質があるのではないか。
そんな気づきから、私が少しずつ見えてきた「私の提供したいセッションの在り方」を、今回は言葉にしてみたいと思います。
判断せずに聴くことの限界
以前の私は、「判断せずに聴く」ことを大切にしていました。
しかし実際には、完全に判断を手放すことは難しいものです。
人は無意識のうちに「今の話、こういうことかな」と思考をめぐらせています。
そのたびに「判断してはいけない」と自分を抑えつけようとすると、むしろ反動が生じてしまう。
心理学ではこれを心理的リアクタンスと呼びます。
禁止されるほどに、かえってその行動に引き寄せられてしまう心の働きです。
判断を「扱う」ことを学ぶ
そこで私は、判断を「してはいけないもの」ではなく、「扱い方を工夫するもの」として捉え直してみました。
セッション中に「今、判断しているな」と気づいたら、ノートに書き出すようにしています。
そうすると、不思議とその判断に固執しなくなるのです。
書き出すことで「これはただの思考」と距離を取れるのかもしれません。
そして、その判断はセッションに活かせることもあります。
話し手と聴き手は、見ている世界が少しずつ違います。
別の人間だからこそ見える視点もあり、その違いの中に気づきのヒントがある。
判断から生まれる問いを「仮説」として扱う
だからこそ、判断から生まれた問いを仮説として扱い、
「こういうことですか?」と話し手に確かめるようにしています。
上からでもなく、下からでもなく、同じ立ち位置で。
その姿勢が「withoutジャッジメント」に近いのかもしれません。
聴き手の役割は、答えを与えることではなく、
話し手が自分の中にある答えに気づけるよう、問いを差し出すこと。
そのためには、聴き手の判断を否定するよりも、丁寧に取り扱うことが大切だと感じています。
あえて事情を尋ねすぎない理由
また最近は、「事情をあえて尋ねすぎないこと」にも意味があると感じています。
もともとは詳細をたずねる必要がないと考えていました。
今では、詳細をたずねてはいけないのではないかと考えています。
話し手の背景を深く知りすぎると、感情が動いてしまう。
理不尽さを感じたり、同情や共感が強く湧いたりすると、
聴き手としての中立性やメタ認知が崩れてしまうことがあります。
感情が揺れること自体は悪いことではありませんが、
「話し手の気づきを支える立場」であるなら、少し距離をとる方がいい。
それが聴き手としての深さを生み出すのだと思います。
近しい人を聴くことが難しい理由
そう考えると、近しい人の話を冷静に聴けない理由も見えてきます。
「利害関係が濃いから」だと考えていましたが、「感情が動いてしまうから」という軸もあるのではないかと思えてきました。
近しいほど相手の出来事に自分を重ねてしまい、感情的になります。
そうなると冷静に話を聴くことが出来なくなってしまいます。
それでは新たな気づきは生まれにくいのではないでしょうか。
私が提供しているセッションは利害関係が濃く、感情が動く相手程私の力は発揮できないのかもしれません。
私の聴くセッションとは、話し手が安心して自分を見つめ直す時間をつくること
私が提供したいセッションとは、
話し手が自分自身をメタ認知できるように支援する場です。
否定も肯定もしない。
ただ一緒に思考を吟味し、客観視を促す時間。
そのためには、聴き手が自分の感情を保留し、
あくまで第三者としての余白を持つことが大切なのだと思います。
この余白についてもう少し詳しくみてみます。
セッションに余計な感情が入り込まないと、話し手に対してフラットでいられます。
フラットでいられると、話し手を評価したくなりません。
評価されないことで、話し手は安心して話せるのではないでしょうか。
否定されたら話したくないですし、強く肯定されても「この人はこんな話をしたら喜んでくれるんだな」と優等生発言をしたくなります。
私が自分の感情を保留して余白をもつことで、話し手の気づきが加速し深まる。
私が提供する聴くセッションはそう在りたいと思います。
オンライン・顔出しなしで聴くことの可能性
そう考えると、今提供しているオンライン・顔出しなしというセッションにはかなりの優位性があると思います。
直接会わず、顔も見ないことで、
余計な感情の揺れを減らし、純粋に「聴く」ことに集中できる。
オンライン・顔出しなしセッションは余計な情報をある程度シャットアウトしてくれます。
おわりに ー 聴くという余白の形
わたしがセッションで出来ることは、
「判断をなくす」のではなく、「判断と判断保留の間で問いを見つける」こと。
今はその間の往復が楽しく、意味があるものと思えます。
往復の多さなのか往復の距離なのか、その余白が多いほど良いセッションを提供できる気がしています。
そこの精度が高まっている実感があります。
そんな私でよければ、是非あなたの話をお聴かせください。
おすすめ記事
聴くことについてコミックになぞらえて真剣に考えた記事はコチラ↓
聴くこと、それは操作系念能力|能力発動条件|悪意ある操作系能力者から身を守る方法
聴くセッションでは話の詳細を尋ねる必要はない、むしろ不要と考えた記事はコチラ↓
話の詳細を聞くか聞かないか問題|この質問で話し手の語りが深くなるか?|聴く人の独り言8
問いの大事さに気付いた記事はコチラ↓
セッションの空気が確かに変わった|聴く人の独り言6
近しい人の話は聴きづらい、けどぴょん吉は妻の話が聴きたい↓
家族の話を聴く|ぴょん吉は妻の話を聴きたい|妻の話だって聴けるはず|聴く日記1
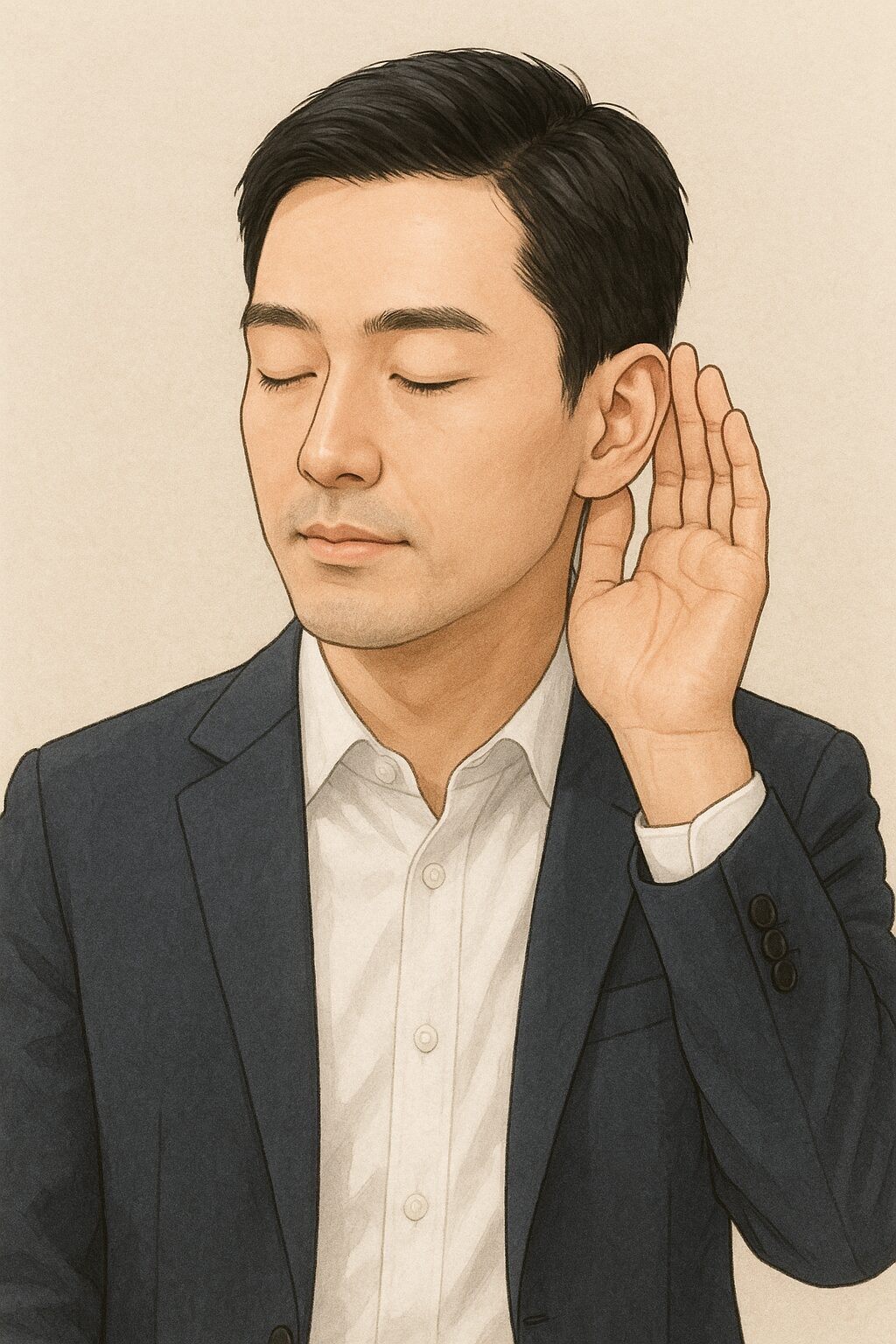

コメント